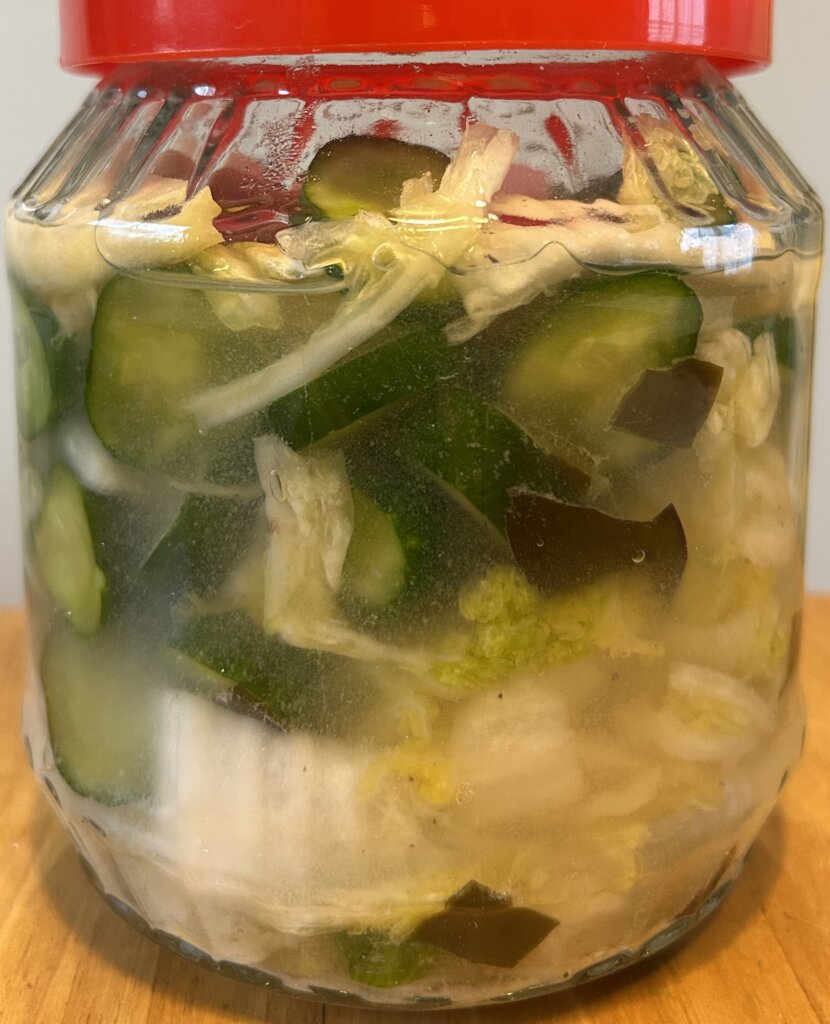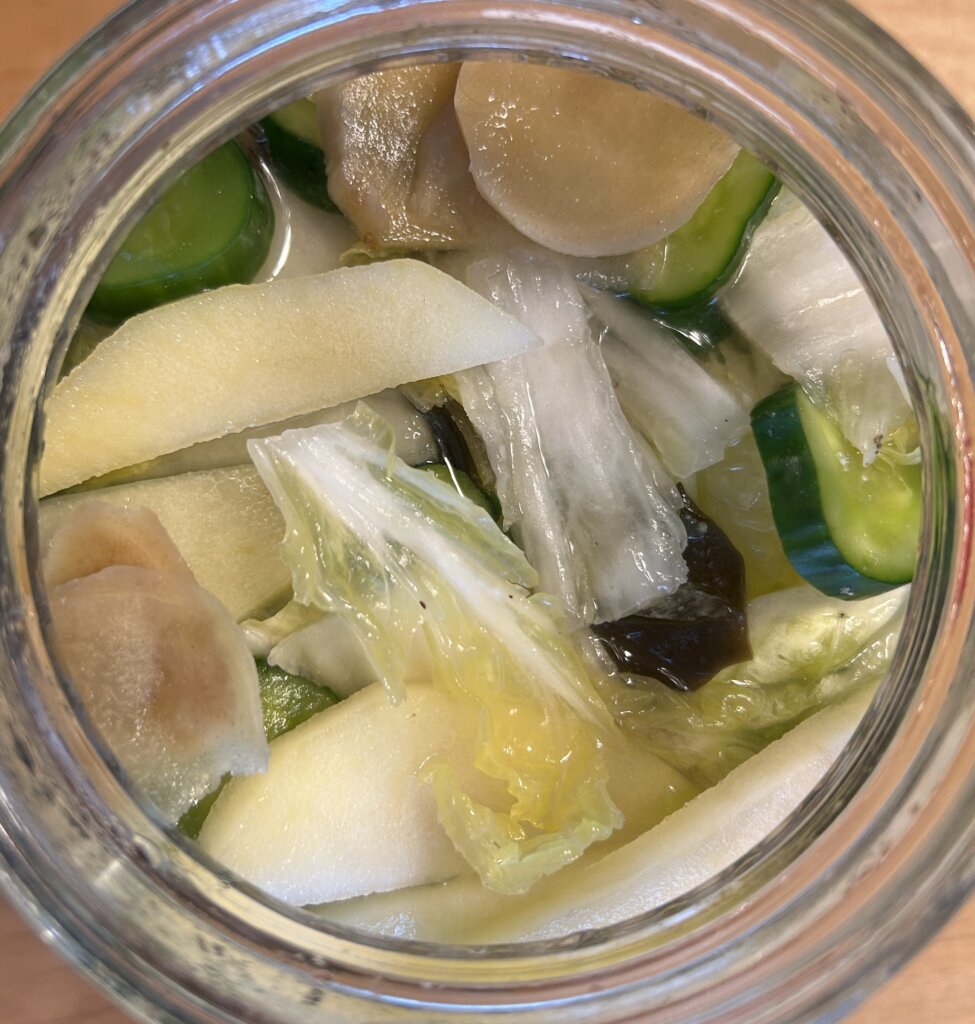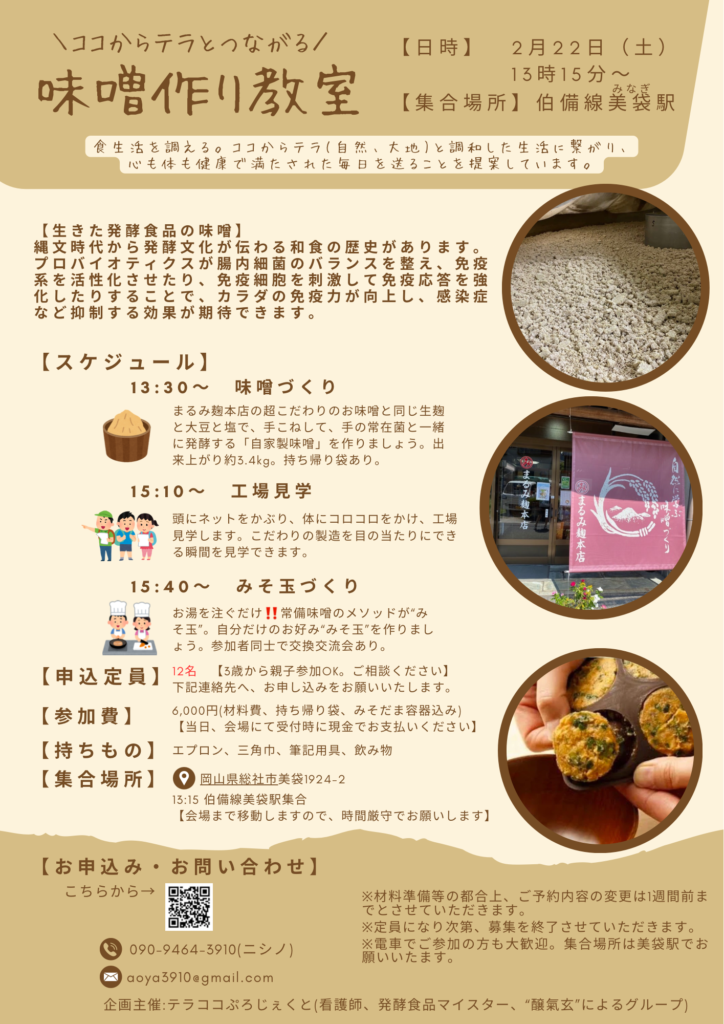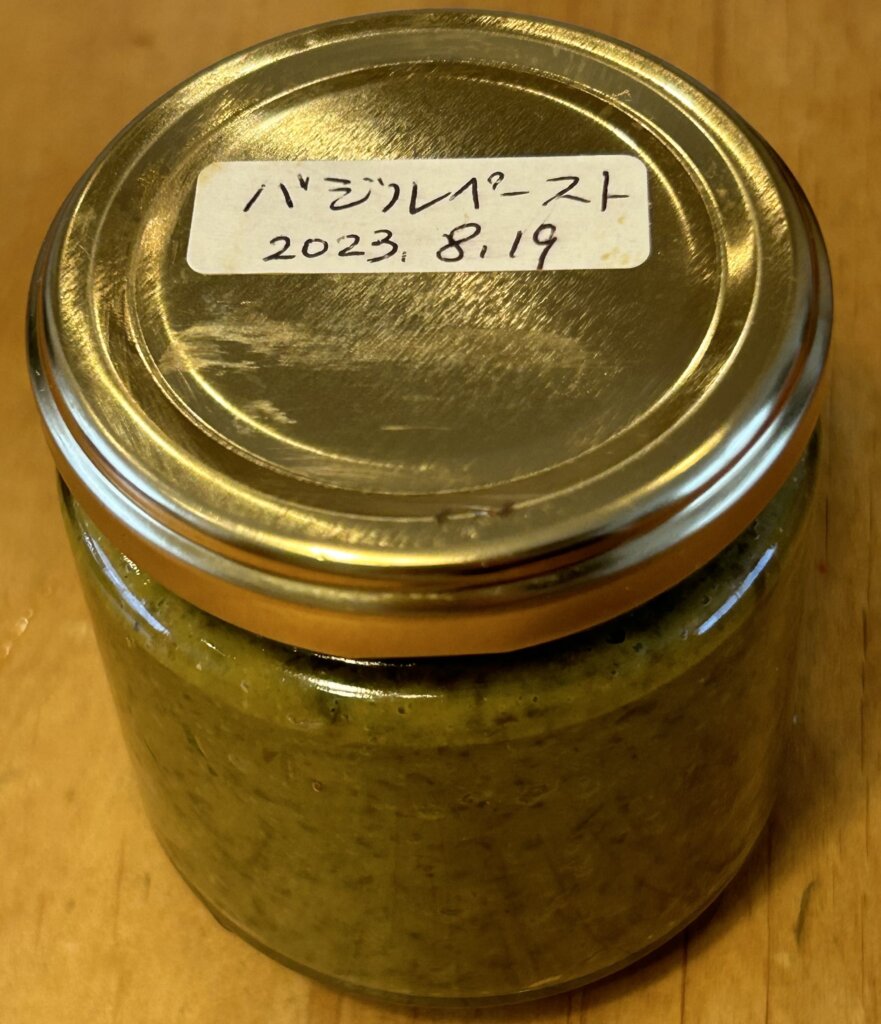#PR
先日、知り合いから一本の焼酎をいただいたんです。
「猫蔵くん、これ、ほんっとに美味しいから。一度飲んでみて。」
「え?!ほんとですか」
私は普段、ほとんどお酒を飲まないんですが、
“そこまで言うなら”
麦焼酎…どんな世界が広がっているんだろう?”
とても興味がわいてきます。
そっと栓を開けてみる―
その瞬間、やさしい麦の香りがふわりと立ち上がる。
まるで「ようこそ」と迎えられたようで、胸の奥がすこし温かくなるような。
思わず家族と「わぁ~いい香り♡」と顔を見合わせましたよ。
せっかくなので、家族と一緒に
水割り+レモンでいただくことに。
一口。
いや、驚きました。
飲みやすい。
癖がないどころか、軽やかで澄んだ味わい。
するりと喉を通り、じんわり広がる麦の旨み。
──あぁ、これは…。
思わず笑ってしまう一杯だ。
大分麦焼酎「杜谷」。
これは、“ただの美味しいお酒”ではなく、
大切な人と過ごす時間を、そっと豊かにしてくれるお酒 です。
だから今度は、私が誰かに言いたい。
「ほんっとに美味しいから、一度飲んでみて!」
お歳暮にも。
忘年会にも。
新年会のホームパーティーにも。
この一本があるだけで、場の空気がやわらかくほどけていくような、
そんな魔法のような焼酎― この年末、私からのイチオシです。
気になった方はぜひこちらから↓↓
大分麦焼酎「杜谷」

焼酎とは・・・
焼酎は、「醸す → 蒸留する」という
日本ならではの二段構造で生まれるお酒です。
まず、麹と酵母によって麦を“醸し”、
日本酒と同じようにアルコールと香りが育ちます。
そして、その液体を蒸留することで──
香りや旨みがぎゅっと濃縮され、保存性も高まります。
発酵がつくりだした世界を、
一度“蒸気”にして再び液体へ戻す。
この工程が焼酎の澄んだ香りと軽やかな味わいを生みます。
大分麦焼酎「杜谷(もりや)」のやさしい飲み口は、
この発酵と蒸留の調和がつくる、まさに日本の技の結晶なのです。